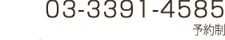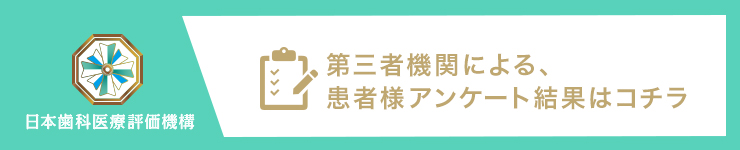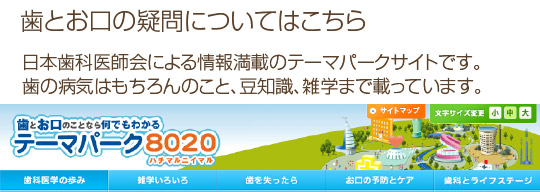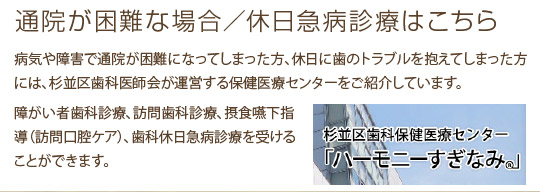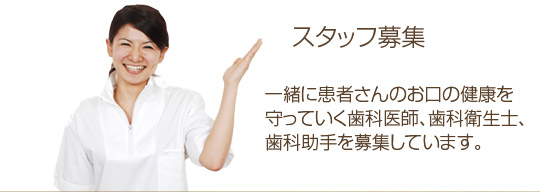12/28(日)~1/4(日)は休診日となります。
よろしくお願いいたします。
年別アーカイブ: 2025年
夏季休暇のお知らせ
8/10(日)~8/17(日)は休診日となります。
よろしくお願いいたします。
接遇研修を実施
2025年6月11日(水)に、分院の東京歯内クリニックにて医療法人合同研修会が行われ、講師に北原文子先生をお招きして医療の接遇研修を行いました。
「接遇を学ぶ」というとマニュアルや型といった画一化されたものを学ぶと想像してしまいますが、医療機関においては心身に痛みや苦痛、不安を抱えている方に対して提供する側面があり、表面的な接遇では真に心に寄り添ったものになりません。医療人としての基本は当然のこと、患者さんのために何ができるか、相手にどのように伝わるかを意識する必要があります。その内容を非言語コミュニケーション・言語コミュニケーションと整理して、それぞれを学びました。
次回は6月27日(金)に実施予定で、午後は休診になります。皆さまのご理解とご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

日本歯周病学会学術大会に参加
2025年5月23-24日に、沖縄県那覇文化芸術劇場なはーと・ホテルコレクティブにて第68回春季日本歯周病学会学術大会が開催され、院長およびスタッフ2名が参加いたしました。
大会期間中に沖縄が梅雨入りとなり、天気が急変しやすい時期ではありましたが、2会場で盛大に行われた学術大会を通じて最新の知見を学んでまいりました。エルビウムヤグレーザーを用いた歯周病治療、インプラント治療の有効性について目を見張るものがあり、当院でも昨年導入した最新機器の臨床的な治療の可能性を学ぶことができました。
引き続き皆様に最善・最良の医療を提供してまいります。
診療業務を分院に移転しました
平素よりご紹介いただいている歯科医院の先生方には大変お世話になっております。また、根管治療をご希望で来院された皆さまや、根管治療について検索する中で当院のホームページに辿り着いた方におかれましては、ご縁いただき誠にありがとうございます。
アメリカでの専門医取得後、川勝歯科医院にて15年間、ご紹介の患者さんの根管治療を行なってまいりました。この度、同じ荻窪にて歯内治療専門の歯科医院「東京歯内クリニック」を開設し、診療を行なっていくこととなりました。開設に伴い最新の医療機器を導入するとともに、勤務医の歯科医師とともにより一層歯内治療を国民の皆様にお届けする体制を整えました。
今後は川勝歯科医院はもちろんのこと、他の医療機関、病院歯科とも連携を取り、日本における診診連携・病診連携の一つのあり方を示すロールモデルとなるべく誠心誠意診療を行なってまいります。「東京歯内クリニック」での診療をご希望の方は、現在のかかりつけ歯科医院にてご相談いただき、紹介状を作成いただいた上でお電話またはwebにてご予約をお取りください。また、かかりつけ歯科医院がない場合は治療相談も行なっております。どうぞお気兼ねなくお問い合わせいただければと思います。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
https://www.tokyo-endodontics.com/

GWの休診日のお知らせ
当院は暦通りの休診日となります。
(通常通り、木曜日も休診です)
よろしくお願いいたします。
JOF酒田交流会に参加
2025年3月29日、30日と、山形県酒田市日吉歯科診療所にてジャパンオーラルフィジシャンフォーラム(JOF)主催酒田交流会が行われ、理事として参加いたしました。
2日間のプログラムの中で、75期に参加されている歯科医院の発表、熊谷崇先生の講演、100症例をこなした先生方の発表があり、メディカルトリートメントモデルに基づいて治療を行うやりがい、難しさを語り合いました。
4月からは第76期のOP育成セミナーが開始されます。引き続き予防歯科にも関わりながら歯の保存、歯髄の保存について共有していきたいと思います。
プロフェッショナルセミナーに参加
2025年2月6日および27日に、株式会社コサカのセミナールームにて「歯科医院で取り組める口腔健康管理」(講師:北原文子先生)が行われ、院長およびスタッフ6名が参加いたしました。
セミナーでは予防メンテナンスを提供する上で技術的なヒントや、所作・言葉遣いの配慮など、多岐にわたる内容で、実践的な学びと気づきを得ることができました。世の中ではAIや自動化の波が広がり、働き方が変わりつつありますが、処置を施すという立場の歯科医師・歯科衛生士の仕事の価値を再確認するとともに、「もっとできることがある」と視野の広がる思いをスタッフとともに共有することができました。
東京科学大学大学院講義にて講義
2025年2月20日に、東京科学大学歯髄生物学分野(興地隆史教授)大学院講義に講師としてお招きいただき、講演いたしました。
講義では「根管洗浄法の選択肢と課題」として、私自身の研究テーマであった根管洗浄を取り上げました。近年では、根管洗浄の効率化を期待するべく、従来のシリンジ洗浄に加えて超音波、音波、レーザーなどによる攪拌が考察されています。研究ではそれらのデブライドメント効果や安全性が考察されていますが、臨床においてはその装置の活用範囲や導入コストも気になります。講演を通じて、私自身が日々の臨床で疑問に思っていることや、臨床現場の医療ニーズから大学の研究シーズのヒントになるようなことを共有いたしました。
大学院講義の後は、興地教授や医局員の皆様と懇親会で親睦を深めました。この度は講師としてお招きいただき、誠にありがとうございました。